仕事の疲れが限界だったある休日
その日、目が覚めた瞬間から身体が重く、まるで鉛のようにベッドに沈んでいました。前日までの仕事の疲れが全身に残っていて、頭もぼーっとして、起き上がるのも一苦労。時計を見ると、もう10時を過ぎていて、普段の自分ならとっくに活動している時間なのに、その日はどうしても布団から出られませんでした。
「今日は休みなんだから、のんびりしよう」と自分に言い聞かせても、心の中にはずっとモヤモヤがあって、「何かやらなきゃ」「無駄に過ごしてるんじゃないか」っていう焦りのような気持ちが抜けませんでした。
特にここ最近は、仕事でのプレッシャーや人間関係のストレスが積もり積もっていて、平日は帰宅後すぐ寝るだけの生活。趣味にも手がつかず、ご飯を食べるのさえ億劫な日もあったほどです。これは、バーンアウト(慢性的な仕事ストレスがうまく管理されないことで生じる職業性の症候群)に近いサインでもあります[1]。
ベッドの中で天井を見つめながら、「このままじゃダメだな」とふと思いました。ちゃんと休めていない自分に気づいた瞬間でした。休日なのに、何かに追われているような感覚。休むための時間が、逆にストレスになっている。
そのとき、「今日は“何もしない日”にしてみよう」と決めました。予定も、タスクも、やらなきゃと思っていたことも、すべて手放す。そう決めた瞬間、少しだけ肩の力が抜けたような気がしました。
今思えば、この「何もしない」と決めた朝が、私にとってストレス発散の第一歩だったのかもしれません。

何もしない日
以前の私は、「何もしないで過ごす休日」に強い罪悪感を抱いていました。せっかくの休みなのに、何か生産的なことをしないと時間を無駄にしているような気がして、いつも心が落ち着かなくて。ダラダラとテレビを見ているだけでも、「こんなんでいいのか?」って自問自答してしまうんです。
特に仕事が忙しい時期は、「休んでる場合じゃない」「もっと成長しなきゃ」「せめて資格の勉強ぐらいしないと」と自分を追い込みがちでした。SNSを開けば、休日をアクティブに過ごしている人たちの投稿が目に入り、比べる必要なんてないのに、どこかで劣等感を感じていました。
そんな私は、常に“何かしていないといけない病”にかかっていたのかもしれません。予定がないと不安になる。やることリストを埋めないと落ち着かない。そんな日々が続いていたある日、ふと体調を崩したんです。特別に風邪を引いたわけでもなく、ただ倦怠感が抜けず、何をしても集中できない。心も体も空っぽな感じでした。
そのとき初めて、「休むこと」って意外と難しいことなんだなと気づかされました。そして、「何もしないこと」は怠けではなく、回復のための大事な時間。仕事から心理的デタッチメント(意図的に「仕事のことを考えない」状態)をとることは、健康やパフォーマンスにとって重要だとする研究もあります[9]。また、仕事や学習の合間にとるマイクロブレイク(10分以内の短い休憩)は疲労軽減や活力の向上に有効だとするメタ分析もあります[8]。
今でも時々、何もしていないとソワソワすることはありますが、それでも「今日は何もしないと決めた日だ」と意識的に受け入れるようにしています。むしろ、そうやって自分に許可を出せるようになったことで、休日の過ごし方がぐっと楽になりました。
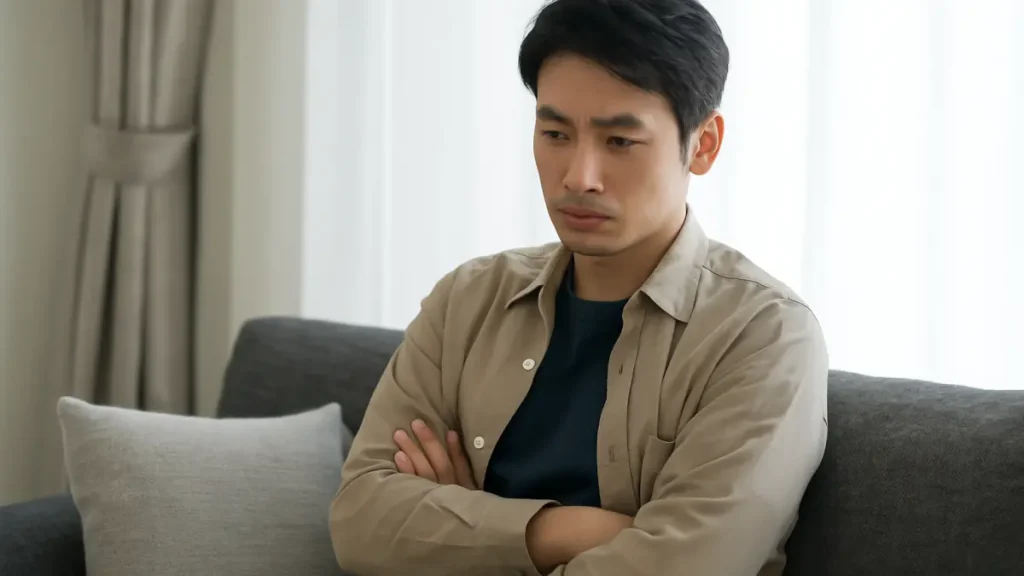
本気で自分を癒す休日
ある日曜日のことでした。朝から何をする気にもなれず、スマホをいじりながらベッドに寝転んでいた私。ふと画面に映ったのは、友人の「温泉でリフレッシュ中〜」というSNSの投稿でした。湯気に包まれた露天風呂の写真とともに、「やっぱり定期的なリセットって大事」と書かれた一言。その瞬間、なぜか胸がズキッと痛んだんです。
「自分、ちゃんと休めてるか?」
その問いが頭をよぎりました。思えば、ここ最近の休日は疲れ切った身体をなんとか横たえるだけ。仕事のことを考えながら無理やり買い物に行ったり、結局ダラダラとテレビを見て終わったり。「これって本当に休めてるのかな?」と、改めて疑問に思ったんです。
そこから急に「今日という日を、自分のために本気で癒す日にしよう」と思い立ちました。何か特別なことをするわけではなく、「ちゃんと心と身体が回復するような時間を過ごそう」と決意したんです。
まずはスマホを置いて、カーテンを開けて朝日をしっかり浴びました。概日リズム(体内時計)は光の影響を強く受け、朝の光は体内時計を前進させて日中の覚醒を助けます[2][3][4]。それだけで、少し気持ちが前向きになれた気がしました。次に、コンビニではなく近所のパン屋でちょっと良い朝食を買って、公園のベンチでゆっくり食べてみる。自然の中で過ごす時間は、気分の改善やストレス低下と関連することが示されています[5][6]。
「休日って、こういうことで良いんだ」
そんな小さな気づきが、私にとっては大きな転機になりました。
“本気で癒す”というのは、豪華な旅行に行くことでも、何かを成し遂げることでもなく、自分の心と体が喜ぶように、丁寧に過ごすことなんだと実感した瞬間でした。
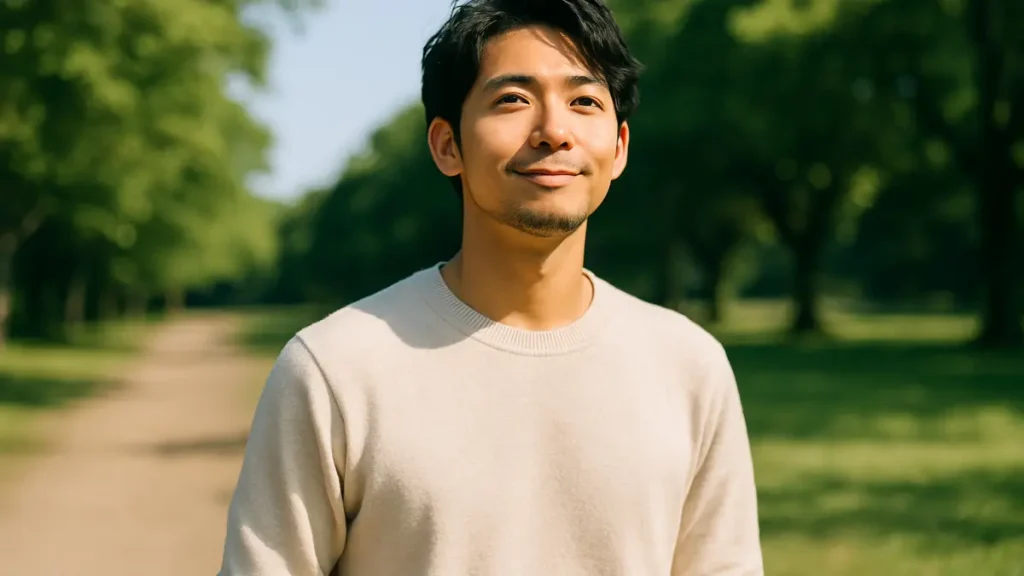
朝一番の“外の空気”
本気で自分を癒す休日を作ろうと決めた翌週、私は早起きして、何も考えずに外に出てみました。目的もなく、ただ外の空気を吸いたくなったんです。
近所の公園まで歩く道のりで、空はやわらかい水色で、風が少し冷たくて心地よかったのを覚えています。呼吸を深くすると、冷たい空気が肺に入ってきて、それがなんだか自分の中のモヤモヤをかき出してくれるような感覚でした。
公園に着いて、ベンチに座ってしばらくじっとしていたんです。すると、思考が自然と静かになっていって、いつも頭の中をぐるぐるしていた仕事の悩みやタスクのことが、ふわっと遠くに感じられたんですよね。こうした朝の屋外光は、夜間の寝つきや翌朝の眠気を改善し得るという介入研究もあります[7]。
普段、朝は目覚ましに叩き起こされて、バタバタと準備して家を飛び出すだけ。でもこの日は、自分の意思で外に出て、ただ空気を感じている。その違いだけで、こんなにも心が落ち着くものなんだと驚きました。
しかも、朝の空気って、まだ誰のものでもないというか、すごく純粋なんですよね。人の声も、車の音も少なくて、空気が透き通ってる感じ。静けさの中に包まれて、自分の内側に自然と意識が向くんです。
たった15分程度のことでしたが、その日一日、ずっと気持ちが整っていて、普段よりずっと穏やかに過ごせました。それ以来、私は週末の朝、なるべく早く起きて外の空気を吸うことを習慣にしています。
「整える」って、何かを頑張ることじゃなくて、余計なものを手放すことなんだと、この朝の空気が教えてくれました。
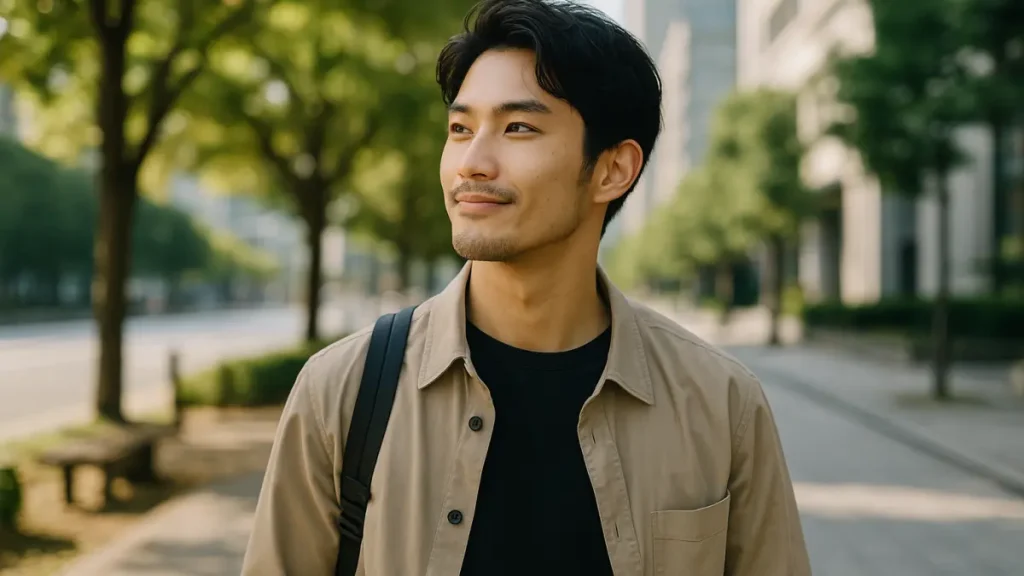
カフェでノートを開く。それだけ
ある休日の午前中、朝の散歩から帰って少しだけ余裕のある気持ちになっていた私は、「もう少しだけ、自分の時間を丁寧に使いたいな」と思って、近所のカフェに行ってみることにしました。
お気に入りのノートとペンだけを持って、カフェの窓際の席に座り、静かにコーヒーを注文。飲み物が届くまでの時間に、ノートを開いて、なんとなく最近のことを書き出してみました。特にテーマも決めずに、「今週はこんなことがあったな」「あのとき少しイラッとしたな」とか、頭に浮かんだことをそのまま。
書いているうちに、ふと気づいたんです。「あれ? なんか気持ちがスッキリしてる」と。こうしたエクスプレッシブ・ライティング(感情や出来事を抑制せずに書く手法)は、精神的・身体的な指標の改善と関連することが複数の研究で示されています[11]。
この日以来、私はよく休日にノートとペンを持ってカフェに行くようになりました。何かを書こうと思わなくても、ページを開くだけで「自分の時間が始まるスイッチ」が入るんです。静かな音楽とコーヒーの香りに包まれながら、ただ自分と向き合う。それだけで、不思議とメンタルが整ってくる。そんな場所と習慣に出会えたことが、私の休日の質を大きく変えてくれました。
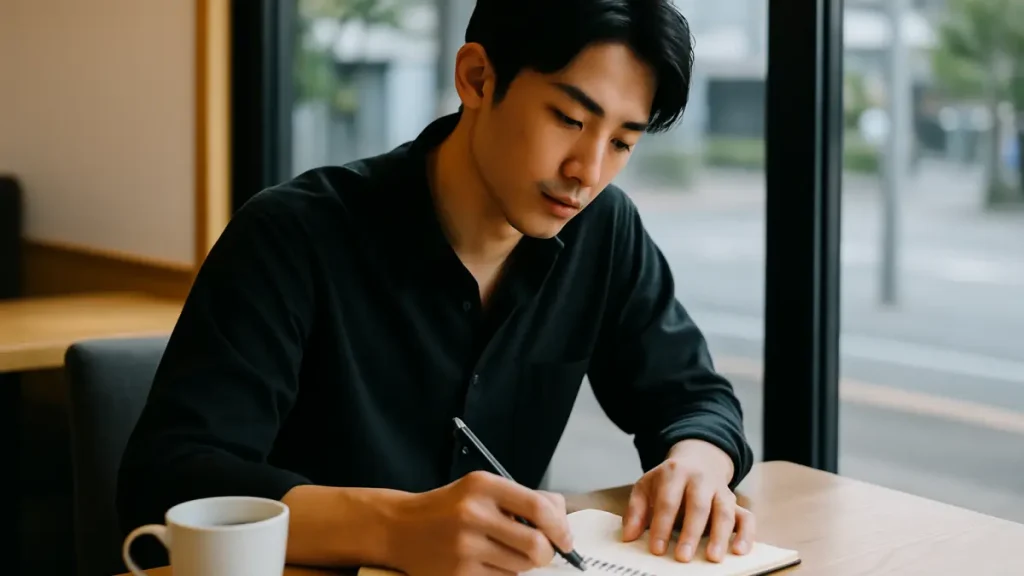
あえて余白時間
以前の私は、休日にもついつい予定を詰め込んでしまうタイプでした。美容院、買い物、部屋の片付け、ジム……「せっかくの休みだから有効活用しなきゃ」と思っていたんです。でも、気づいたら夕方にはぐったり。休んだはずなのに、疲労感だけが残っている。そんな休日が続いていました。
ある日、「今日は何もしない日」と決めて、予定を一切入れずに過ごしてみたんです。正直、最初はちょっと不安でした。「このまま何もせず終わっちゃったらどうしよう」って。でも結果的に、それが想像以上に心地よかったんですよね。
ゆっくり起きて、ベッドの中でスマホも見ずにぼーっとする。朝ごはんをゆっくり噛んで食べる。洗濯はするけど、その合間に本を読んだり、何もせず空を眺めたり。やらなきゃいけないことではなく、「やりたいと思ったらやる」スタンスで過ごすことが、こんなにも気持ちを軽くしてくれるんだと驚きました。
“余白時間”は単なる隙間ではなく、回復のためのスペース。短い休憩でも疲労を和らげ活力を高めうることが示されています[8]。また、仕事から意図的に距離をとる心理的デタッチメントは、心身の健康指標の改善と関連します[9]。

公園で読書
ある休日の午後、ふと「今日は静かに本が読みたいな」と思い立って、近所の公園に向かいました。お気に入りの文庫本と、ベンチに座っても疲れないように小さなクッション、それと水筒に入れたハーブティーをバッグに詰めて。
その日は少し雲がかかっていて、日差しがやわらかく、風も涼しくてちょうどいい気候でした。公園には家族連れやジョギングしている人もいて、にぎやかだけどどこか穏やかな雰囲気。私は木陰にあるベンチに腰掛けて、ゆっくりと本を開きました。
読み始めると、文字がスッと頭に入ってくることに驚きました。自然の中で過ごすことは、反すう思考(同じ嫌な考えが頭の中で繰り返されること)を減らす可能性があることも報告されています[6]。物語の世界に入り込んでいるうちに、仕事で感じていたストレスやモヤモヤが、すーっとどこかへ流れていくような感覚がありました。
1時間が経っても、「あ、もうそんなに経ったの?」というくらいあっという間でした。でも、不思議と体も心も軽くなっていて、「ああ、これでまた明日から頑張れそう」って思えたんです。

SNS断ちしてわかった“情報疲れ”
ある休日の朝、いつものように布団の中でスマホをいじっていた私は、ふと気づいたんです。気づけばInstagram、X(旧Twitter)、YouTube、TikTokを無意識に行ったり来たりして、1時間以上経っていました。その間、何を得たかといえば、特に記憶にも残らない投稿と、どこか胸がざわつくような「焦り」だけ。
「このままで本当にいいのかな…?」それが、私の“SNS断ち”のきっかけでした。思い切ってアプリを削除し、まずは数日間のデジタル・デトックス。ランダム化比較試験では、ソーシャルメディアの使用を1日合計30分程度に制限すると孤独感や抑うつが軽減したり、1週間の使用休止で幸福感・抑うつ・不安が改善したりする結果が報告されています[12][13]。
数日を過ぎると、朝の気分が軽くなり、時間がゆっくり流れるように感じました。読書や料理など、「自分のための時間」を純粋に楽しめるようになったのです。

休日ルーティンを整えたら、平日が軽くなった
以前の私は、休日になると生活リズムが一気に崩れてしまっていました。夜更かし、遅起き、食事は適当、やることはその場の気分任せ。気づけばあっという間に日曜の夜になり、月曜の朝は寝不足と疲労感でスタート…。そんな生活を何度も繰り返して、「このままじゃずっとしんどいままだ」と感じたんです。
そこから少しずつ、自分なりの「休日ルーティン」を整えることにしました。まずは「朝だけ整える」ことから。土日ともに、なるべく同じ時間に起きて、カーテンを開けて光を浴び、白湯を飲む。規則的な就寝・起床時刻は、質の良い睡眠習慣に不可欠とされます[10]。また、平日と週末の睡眠時刻差による社会的時差(ソーシャル・ジェットラグ)は、気分や健康指標の悪化、炎症マーカーの上昇と関連する研究もあります[11]。
夕方以降はなるべく画面から離れて、紙の本を読んだり、音楽を聴いたりして過ごすようにしたところ、日曜の夜特有の重さがかなり減りました。夜の強い光やデバイスの光は体内時計を遅らせ、眠りを妨げるため、夜は光を控えめに、日中は適度に光を浴びるという光のマネジメントも意識しています[3]。
こうして休日を丁寧に過ごすようになってから、平日のスタートが本当に軽くなったんです。月曜の朝もスッと起きられて、心に余裕をもったまま一週間を始められる。これには自分でも驚きました。
“休み方”は、想像以上に大事。整った休日が、整った平日をつくる。その実感を日々かみしめながら、自分だけのルーティンをこれからもアップデートしていきたいと思っています。

「頑張らない休日」を取り入れて変わった自分
以前の私は、休日さえも「何かやらなきゃ」と思い詰めて過ごしていました。掃除して、買い物して、ジム行って、自己啓発本を読んで…と、「せっかくの休みを有効活用しないと」って、自分にプレッシャーをかけ続けていたんです。
でも、そんな“頑張る休日”を繰り返していたある日、ふと気づいたんですよね。「あれ? 全然休めてない…むしろ平日より疲れてるかも」って。
思い切って、その翌週は“何もしない休日”を作ってみました。予定はゼロ。目覚ましはかけずに自然に目が覚めるまで寝て、朝ごはんは冷蔵庫にあるもので済ませて、部屋着のまま一日過ごす。
最初はちょっと不安でした。「こんなにダラけてていいのかな?」って。でも、不思議なことに、何もしてないはずなのに、心がどんどん軽くなっていったんです。気がつけば、肩に乗っていた“ちゃんとしなきゃ”という重荷がスーッと取れていくような感覚。
それからは、「頑張らない日」を定期的に取り入れるようにしました。何かを成し遂げなくても、誰かに褒められなくても、“ただ生きているだけでいい日”を自分に許すことで、驚くほど気持ちが安定するようになったんです。むしろ、しっかり休んだあとの平日は、集中力も上がって前向きになれる。
「休むこと」も、大切な仕事の一部。
参考文献
- World Health Organization. Burn-out an “occupational phenomenon”. https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/burn-out-an-occupational-phenomenon
- National Institute of General Medical Sciences (NIH). Circadian Rhythms (Fact Sheet). https://www.nigms.nih.gov/education/fact-sheets/Pages/circadian-rhythms
- National Heart, Lung, and Blood Institute (NIH). Circadian Rhythm Disorders – Treatment. https://www.nhlbi.nih.gov/health/circadian-rhythm-disorders/treatment
- Blume C, et al. Effects of light on human circadian rhythms, sleep and mood. Clocks & Sleep. 2019. (PMC6751071) https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6751071/
- White MP, et al. Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing. Scientific Reports. 2019;9:7730. https://www.nature.com/articles/s41598-019-44097-3
- Bratman GN, et al. Nature experience reduces rumination and subgenual prefrontal cortex activation. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2015;112(28):8567–8572. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1510459112
- He M, et al. Morning bright light improves nocturnal sleep and next-day alertness. (Field intervention study). 2023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36058557/
- Albulescu P, et al. “Give me a break!” A systematic review and meta-analysis on the efficacy of micro-breaks for increasing well-being and performance. PLOS ONE. 2022;17(8):e0272460. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0272460
- Wendsche J, Lohmann-Haislah A. A meta-analysis on antecedents and outcomes of psychological detachment from work. Frontiers in Psychology. 2017. (PMC5233687) https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5233687/
- Centers for Disease Control and Prevention. Sleep and Health: Model and encourage habits that promote good sleep. 2024. https://www.cdc.gov/physical-activity-education/staying-healthy/sleep.html
- Girtman KL, et al. Later sleep timing and social jetlag are related to increased inflammation in adults. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2022. https://jcsm.aasm.org/doi/pdf/10.5664/jcsm.10078
- Hunt MG, et al. No More FOMO: Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression. Journal of Social and Clinical Psychology. 2018;37(10):751–768. https://guilfordjournals.com/doi/10.1521/jscp.2018.37.10.751
- Lambert J, et al. Taking a One-Week Break from Social Media Improves Well-Being, Depression, and Anxiety: A Randomized Controlled Trial. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. 2022. https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cyber.2021.0324


